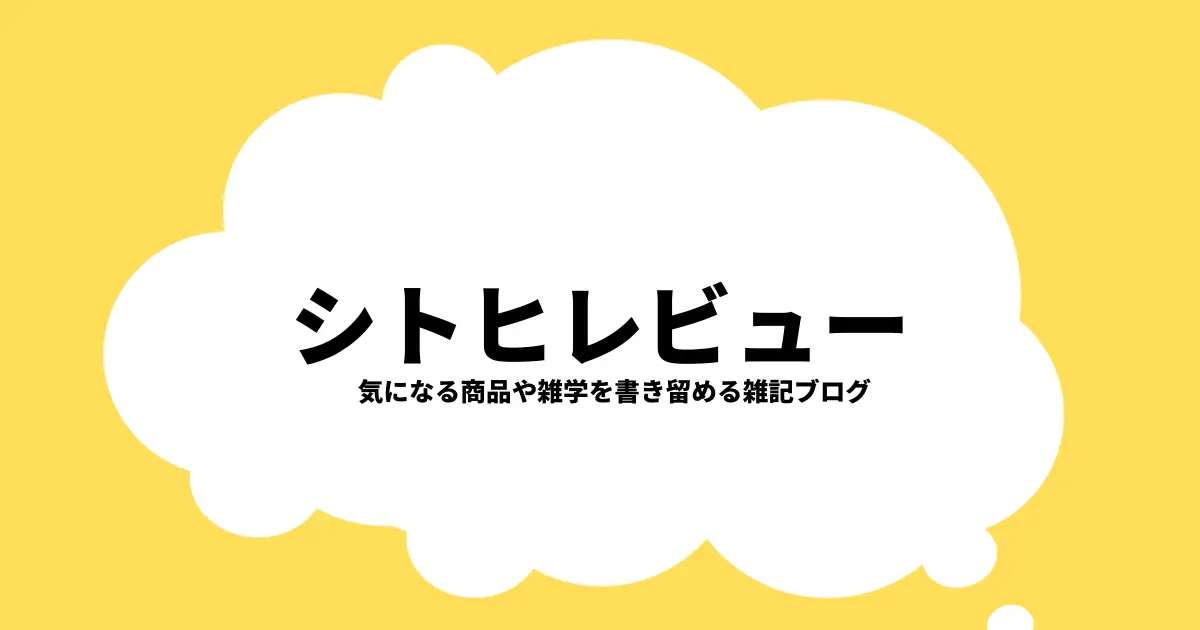私たちが写真撮影のときに当たり前に使っている「はいチーズ」という掛け声。この言葉に、実はあるアメリカ大統領の政治戦略が隠されていたという驚きの説があります。
普段何気なく口にしている言葉の裏には、意外な歴史が隠されているものです。この記事では、その政治戦略説の真相と、日本で「はいチーズ」がどのように定着していったのか、その背景を詳しく解説します。
そもそも「はいチーズ」の本当の意味
多くの人が知っているようで知らない、「はいチーズ」の本来の意味や世界の事情を見ていきましょう。なぜ「チーズ」なのか、その理由を知ると納得するはずです。
なぜ「チーズ」と言うのか|笑顔を作る魔法の言葉
結論から言うと、「チーズ」と言うのは自然な笑顔を作るためです。これは英語の「Cheese」という単語の発音が大きく関係しています。
英語で「Cheese」と発音するとき、最後の「ee(イー)」という音は、口角が自然に横に広がり、歯が見える状態になります。これが、まさしく笑顔の形そのものです。私も試してみましたが、「チー」と伸ばすだけで、意識しなくても口角が上がります。
写真を撮られる側が緊張して硬い表情になってしまうのを防ぎ、誰でも簡単に笑顔の写真を撮れるようにするための、実によくできた「魔法の言葉」です。この発音こそが、写真写りを良くするカギとなっています。
世界も同じ?各国のユニークな掛け声
世界中で「はいチーズ」が使われているかというと、そうではありません。しかし、「笑顔になる言葉」を掛け声にするという目的は共通しています。
国や地域によって、その土地ならではのユニークな言葉が使われています。発音が笑顔に似る単語や、「イー」の音を含む単語が選ばれる傾向が強いです。
| 国・地域 | 掛け声 | 日本語訳 |
|---|---|---|
| 韓国 | 김치(キムチ) | キムチ |
| 中国 | 茄子(チエズ) | ナス |
| スペイン | Patata(パタタ) | ジャガイモ |
| フランス | Ouistiti(ウィスティティ) | 小型のサル |
| ドイツ | Spaghetti(スパゲッティ) | スパゲッティ |
このように、必ずしも「チーズ」ではありません。韓国の「キムチ」も、最後の「チ」の音が笑顔を作るのに役立っています。文化の違いが見えて非常に興味深いです。
驚きの由来説|「はいチーズ」は政治戦略だった?
「Say cheese」の由来には、単に笑顔を作るという理由だけでなく、もっと政治的な意図があったとする説が存在します。これが本当だとしたら、かなり驚きの背景です。
発端はアメリカ大統領?
「Say cheese」の由来として、時折語られるのが政治的な説です。その中心人物は、アメリカ第32代大統領フランクリン・ルーズベルトだと言われています。
彼は在任中にポリオ(小児麻痺)を患い、下半身が不自由になりました。当時のアメリカにおいて、強いリーダーシップが求められる大統領の弱々しい姿は、国民の不安を煽るものでした。
そこで、公の場で写真撮影される際、ポリオによる苦痛な表情を隠し、常に自信に満ちた笑顔を見せる必要があったとされています。そのために、強制的に笑顔を作る「cheese」という言葉を使わせ始めた、という都市伝説的な説です。これが「政治戦略」と呼ばれる理由です。
この説の信憑性は?
しかし、私が調査した限り、このルーズベルト大統領の政治戦略説は、現在では俗説と見なすのが妥当です。
この説を明確に裏付ける信頼できる歴史的資料は、実のところ見当たりません。1940年代頃から「Say cheese」という表現が使われ始めた形跡はありますが、それがルーズベルト大統領の指示だったという証拠は乏しいです。
むしろ、「ee」の発音が自然な笑顔を作るという音声学的な理由の方が、はるかに合理的で広く認知されています。政治戦略説は、言葉の由来にまつわる「興味深い一つの説」として楽しむのが良いでしょう。
日本で「はいチーズ」が定着した驚きの背景
日本では、本家アメリカの「Say cheese!」とは少し違う「はい、チーズ」という形で定着しました。ここには、日本独自の文化的背景と、ある企業の戦略が大きく関わっています。
きっかけはテレビCMだった
日本で「はいチーズ」が爆発的に広まったのは、戦後の高度経済成長期です。その決定的なきっかけは、1963年(昭和38年)に放送された、雪印乳業(現在の雪印メグミルク)のチーズのテレビコマーシャルでした。
このCM内で使われた「はいチーズ」というキャッチーなフレーズが、お茶の間に一気に浸透しました。当時の日本においてチーズはまだ目新しい食材でしたが、このCMがチーズの認知度向上にも大きく貢献しました。
このCMが、日本の写真文化における定番の掛け声を生み出したと言っても過言ではありません。
なぜ日本独自に「はい」が付いたのか
日本版の「はいチーズ」には、本家にはない「はい」という言葉が頭に付いています。これは、日本語ならではのコミュニケーションの特性が表れた結果です。
この「はい」は、撮影者がシャッターを切るタイミングを被写体に知らせるための「合図」や「間(ま)」の役割を果たしています。「今から撮りますよ、準備してください」という予告と、「笑顔でお願いします」という依頼が、この「はい」の一言に込められているのです。
単なる翻訳ではなく、日本の文化に合わせて最適化された、日本流のアレンジと言えます。
カメラの普及と「笑顔」の文化
CMが放送された1960年代は、日本において家庭用カメラが一般に普及し始めた時期と重なります。これは非常に重要なポイントです。
それまでの写真は、写真館で高価なお金を払い、カチコチに緊張して撮る「記念写真」が主流でした。しかし、誰もが手軽にカメラを持てるようになると、日常の何気ない瞬間や、楽しい旅行の思い出を記録したいというニーズが高まります。
人々が写真に求めるものが「緊張した真面目な顔」から「楽しい瞬間の笑顔」へと変化していきました。「はいチーズ」という掛け声は、まさにこの新しい写真文化の象徴的な言葉として、完璧なタイミングで登場し、広く受け入れられて定着したのです。
まとめ
「はいチーズ」という掛け声は、元々英語の「Cheese」の発音が笑顔を作ることに由来していました。ルーズベルト大統領の政治戦略だったという説は、興味深いものの俗説の可能性が高いです。
日本では、1963年の雪印乳業のCMをきっかけに、「はい」という日本独自の合図が加わって定着しました。家庭用カメラの普及という社会背景とも重なり、私たちの写真文化に深く根付いていったのです。