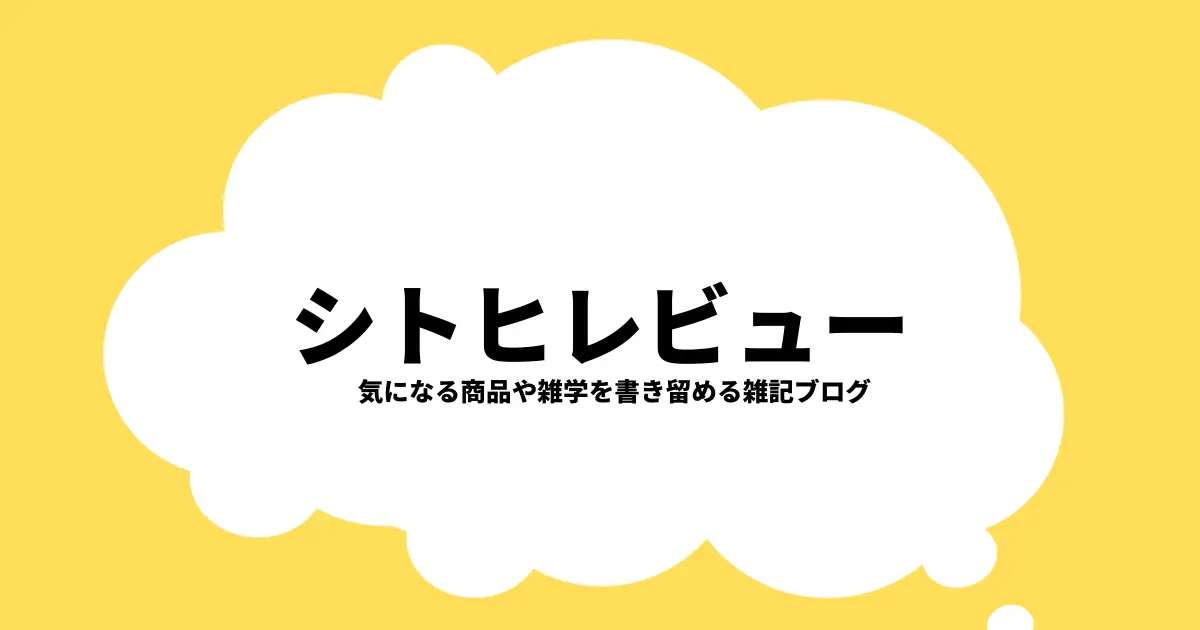毎年やってくる9月1日の「防災の日」。学校や職場で避難訓練が行われることもあり、多くの人が知っている記念日です。しかし、なぜこの日が防災の日になったのか、そして私たちは具体的に何をすれば良いのか、その本質まで理解している人は少ないかもしれません。私自身、過去の災害報道に触れるたび、防災への意識を新たにしてきました。防災は、特別なことではなく、日々の暮らしの延長線上にあるべき大切な備えです。
この記事では、防災の日の由来から、個人や家庭で「今すぐやるべきこと」、さらに社会全体の取り組みまで徹底的に解説します。この記事を読めば、防災の日があなた自身の行動を変えるきっかけになるはずです。
防災の日の由来|なぜ9月1日なのか?
防災の日が9月1日に定められたのには、日本の災害の歴史に根差した、二つの大きな理由があります。それは、過去の大災害の教訓を忘れないため、そして、古くから警戒されてきた自然災害の時期に合わせたものです。
関東大震災|すべての始まりとなった大災害
防災の日の日付を決定づけた最も重要な出来事は、1923年9月1日に発生した「関東大震災」です。マグニチュード7.9を記録したこの巨大地震は、首都圏に壊滅的な被害をもたらしました。死者・行方不明者は10万5,000人以上にのぼり、日本の近代史において最悪の地震災害として刻まれています。
特筆すべきは、犠牲者の多くが地震の揺れそのものではなく、その後に発生した大規模な火災によって亡くなったという事実です。この悲劇的な教訓を決して風化させないために、関東大震災が発生した9月1日という日付が、防災の日として選ばれました。
台風シーズンと二百十日|もう一つの理由
9月1日が選ばれた背景には、もう一つ理由があります。それは、この時期が伝統的に台風の襲来が多い「厄日」とされてきたことです。立春から数えて210日目にあたる9月1日頃を「二百十日(にひゃくとおか)」と呼び、古くから農家の人々は稲の収穫期を前に台風を警戒してきました。
この伝統的な警戒心は、1959年に日本を襲った「伊勢湾台風」によって、近代においても通用する教訓であることが証明されます。戦後最大級の風水害をもたらしたこの台風が、防災の日制定を後押しする直接的なきっかけの一つとなりました。つまり防災の日は、地震と台風という、日本が直面する二大災害への備えを象徴する日なのです。
閣議決定|正式に制定された日
関東大震災から37年、そして伊勢湾台風の翌年である1960年6月の閣議了解によって、9月1日を「防災の日」とすることが正式に定められました。
その目的は、関東大震災の教訓を後世に伝え、台風や豪雨、津波といった様々な自然災害に対する国民の認識を深め、備える心構えを準備することにあります。このように、防災の日は過去を悼むだけでなく、未来の命を守るための実践的な備えを促す国民的な誓いの日として制度化されたのです。
防災の日は9月1日だけじゃない|防災関連の記念日
防災への意識を高めるための取り組みは、9月1日だけに限りません。年間を通じて、災害の教訓に基づいた様々な記念日が設けられています。私が特に重要だと考える日をいくつか紹介します。
防災週間|8月30日~9月5日
防災の日を含む一週間、つまり毎年8月30日から9月5日は「防災週間」と定められています。この期間には、国や地方自治体、企業などが連携し、全国各地で防災訓練や講演会、展示会などの啓発イベントが集中的に実施されます。防災に関する知識を深め、実践的なスキルを身につける絶好の機会です。
津波防災の日|11月5日
2011年の東日本大震災では、津波によって甚大な被害が出ました。この痛ましい教訓から、同年11月5日が「津波防災の日」として制定されました。この日付は、1854年の安政南海地震の際に、稲の束に火を放って村人を高台へ避難させ、津波から救った「稲むらの火」の逸話に由来します。津波からの避難の重要性を象徴する日です。
その他の重要な日|忘れてはならない教訓
公式な記念日以外にも、私たちが忘れてはならない日があります。これらの日は、災害の記憶を風化させず、防災意識を新たにする上で非常に重要です。
| 日付 | 名称・通称 | 契機となった災害 | 主な焦点・活動 |
| 9月1日 | 防災の日 | 関東大震災、伊勢湾台風 | 地震、台風など総合的な災害への備え、全国での防災訓練 |
| 11月5日 | 津波防災の日 | 東日本大震災、安政南海地震 | 津波対策の推進、避難訓練 |
| 1月17日 | 防災とボランティアの日 | 阪神・淡路大震災 | 災害時のボランティア活動や自主的な防災活動への認識深化 |
| 3月11日 | (非公式) | 東日本大震災 | 各地での追悼行事、メディアによる防災特集、訓練の実施 |
これらの日を意識することで、一年を通じて防災への高い関心を持ち続けることができます。
防災のために私たちが「今すぐ」やるべきこと
防災の日を単なる記念日で終わらせないために、私たちが個人や家庭で具体的に行動することが何よりも大切です。ここでは、政府の指針などに基づき、今すぐ取り組むべき5つのアクションを紹介します。
リスクの把握|ハザードマップを確認する
防災対策の第一歩は、自分の住む地域の災害リスクを正確に知ることです。お住まいの自治体が公開している「ハザードマップ」を必ず確認しましょう。
ハザードマップを見れば、どの場所でどのような災害が、どの程度の規模で起こりうるのかが一目瞭然です。これを知らずして、効果的な避難計画は立てられません。
| マップの種類 | 何がわかるか | 活用例 |
| 洪水ハザードマップ | 河川の氾濫による浸水区域と深さ | 大雨時に自宅が浸水するか、安全な避難所はどこかを確認する |
| 内水ハザードマップ | 下水道などからの浸水区域と深さ | ゲリラ豪雨で冠水しやすい道路を避け、安全な避難経路を計画する |
| 土砂災害ハザードマップ | がけ崩れや土石流の危険区域 | 自宅が危険区域内か確認し、警報発令時の早期避難計画を立てる |
| 津波ハザードマップ | 津波の浸水区域、深さ、到達時間 | 揺れを感じたら即座に逃げるべき高台へのルートを把握しておく |
| 地震マップ | 想定される震度や液状化の危険度 | 家具の固定を徹底し、建物の耐震性を確認するきっかけにする |
ハザードマップでリスクを把握したら、それをもとに「いつ」「誰が」「何をするか」を決める個人用の避難計画「マイ・タイムライン」を作成することをおすすめします。
非常用持ち出し袋の準備|命をつなぐアイテム
災害発生時に、命を守るために最低限必要なものをまとめた「非常用持ち出し袋」を準備しておくことは必須です。いざという時にためらわず、迅速に避難するために欠かせません。
リュックサックなど両手が空くタイプの袋に、以下のアイテムを参考に準備し、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。
- 貴重品|現金、身分証明書のコピー
- 避難用品|懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、モバイルバッテリー
- 救急・衛生用品|救急セット、常備薬、マスク、携帯トイレ、除菌シート
- その他|軍手、タオル、下着、ホイッスル、ヘルメットや防災頭巾
防災グッズを一つ一つ揃えるのは大変ですよね。防災士監修の防災グッズ44点セット
![]() なら、基本的な備えが一度で完了するので安心です。
なら、基本的な備えが一度で完了するので安心です。
ご家庭に乳幼児がいらっしゃる場合は粉ミルクやおむつを、女性の方は生理用品などを追加して、ご家庭に合った備えを万全にしましょう。
家庭内備蓄|ライフライン停止に備える
災害発生後、電気・ガス・水道といったライフラインが止まり、支援物資が届くまでには時間がかかります。その間を自力で乗り切るために、家庭内での備蓄が極めて重要です。
政府は最低でも3日分、大規模災害を想定するなら1週間分の食料と飲料水の備蓄を推奨しています。普段食べている缶詰やレトルト食品などを少し多めに買っておき、食べた分を買い足していく「ローリングストック法」なら、無理なく続けられます。
| 優先度 | カテゴリ | 具体的な品目例 |
| 高 | 食料・水 | 水(1人1日3L目安)、アルファ米、レトルト食品、缶詰、栄養補助食品 |
|---|---|---|
| 高 | 生活用品 | カセットコンロ・ボンベ、携帯トイレ、トイレットペーパー、ラップフィルム |
| 中 | 情報・衛生 | 大容量バッテリー、給水袋、ウェットティッシュ、ポリ袋 |
| 低 | その他 | 普段使っている食品や日用品で備蓄できるもの |
食料や水だけでなく、カセットコンロや簡易トイレも備えておくと、避難生活の質を大きく向上させます。
家の安全対策|自宅を要塞化する
地震の際、家の中が最も危険な場所になることがあります。家具の転倒や火災から命を守るため、自宅の安全対策を見直しましょう。
阪神・淡路大震災では、倒れた家具の下敷きになって亡くなった方が多くいました。この教訓から、以下の対策が強く推奨されています。
- 家具の固定|タンスや食器棚、冷蔵庫などをL字金具や突っ張り棒で壁に固定する。
- 火災予防|地震の揺れを感知して電気を自動的に止める「感震ブレーカー」を設置する。
- 構造の確認|自宅の耐震基準を確認し、必要であれば耐震診断や補強工事を検討する。
- 経済的備え|被災後の生活再建のために、地震保険への加入を検討する。
できるところから一つずつでも対策を進めることが、あなたと家族の命を守ることに繋がります。
家族との連携|安否確認と避難計画
災害は、家族が一緒にいる時に起こるとは限りません。離れ離れになった時にどう行動するか、事前に家族で話し合っておくことが、生死を分けることもあります。
災害直後は電話が繋がりにくくなるため、複数の連絡手段を決めておくことが重要です。
- 安否確認の方法|NTTの災害用伝言ダイヤル「171」や、各携帯キャリアが提供する災害用伝言板の利用方法を家族全員で確認しておく。
- 避難計画|ハザードマップで「避難場所」と「避難所」を確認し、集合場所を複数決めておく。
- 情報共有|子どもや高齢者、ペットのことなど、特別な配慮が必要な家族の情報を全員で共有しておく。
定期的に家族会議を開き、万が一の時のルールを再確認する習慣をつけましょう。
社会全体の取り組み|楽しく学ぶ防災訓練
防災は、個人の「自助」だけでなく、地域で助け合う「共助」、行政による「公助」が連携して初めて機能します。ここでは、社会全体で行われている防災の取り組みを紹介します。
学校での防災教育|命を守るスキルを学ぶ
日本の学校では、防災教育が非常に重視されています。地震や火災を想定した定期的な避難訓練は、年々実践的になっています。
例えば、緊急地震速報が鳴った際に「まず低く、頭を守り、動かない」という安全確保行動を瞬時にとるための訓練や、教員の指示がなくても生徒自身が判断して行動する訓練などが行われています。私も子どもの頃に受けた訓練が、防災意識の基礎となっています。
地域での取り組み|防災イベントに参加してみる
近年、子どもから大人まで、誰もが楽しみながら防災を学べるイベントが増えています。堅苦しい訓練だけでなく、こうしたイベントに参加してみるのも良い方法です。
- 防災運動会|バケツリレーや担架リレーなど、運動会の種目に防災の要素を取り入れたイベント。
- ぼうさい縁日|水消火器体験や応急手当などを、縁日のような雰囲気で体験できる。
- 避難訓練コンサート|コンサートの途中で地震が発生したという想定で、観客も参加して避難訓練を行うユニークな取り組み。
お住まいの地域でも、防災週間に合わせて様々なイベントが企画されているはずです。ぜひ情報をチェックして、家族や友人と参加してみてはいかがでしょうか。
企業の防災対策|事業継続と私たちの生活
企業の防災対策も、私たちの生活を守る上で非常に重要です。多くの企業では、災害時にも事業を継続するための計画「BCP(事業継続計画)」を策定しています。
これは、従業員の安全を守るだけでなく、災害後も製品やサービスの供給を止めないことで、社会全体の混乱を防ぎ、経済の回復を支えるという大きな役割を担っています。企業が防災に力を入れることは、巡り巡って私たちの安定した生活を守ることに繋がっているのです。
まとめ
防災の日は、1923年の関東大震災という悲劇的な災害の教訓を忘れず、台風などの自然災害が多発する時期に備えるために制定されました。それは単なる過去の追悼の日ではなく、未来の命を守るための具体的な行動を、国民一人ひとりに促す日です。
大切なのは、防災の日の由来や知識を知るだけで満足せず、それを自分自身の行動に結びつけることです。ハザードマップの確認、非常用持ち出し袋の準備、家庭内備蓄、家具の固定、そして家族との話し合い。やるべきことはたくさんありますが、すべてを一度に行う必要はありません。
この記事をきっかけに、「これなら今日できそうだ」ということを一つでも見つけて、実行してみてください。その小さな一歩の積み重ねが、あなたとあなたの大切な人の命を守る、最も確実な備えとなります。