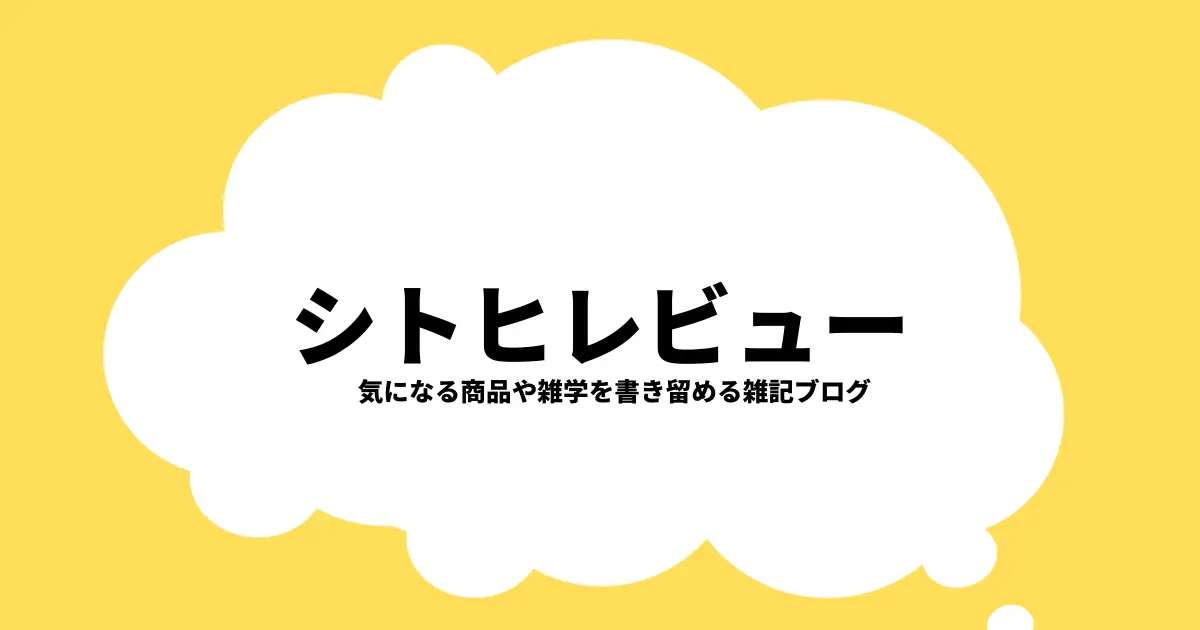中学校の理科の自由研究、テーマ選びに悩んでいませんか。
「どうせやるなら、かんたんで、楽しくて、しかも評価されるものがいい」
そう考えるのは当然です。
この記事では、私が実践している、中学生に最適な「かんたんで楽しい」理科の自由研究テーマの見つけ方と、高評価につながるまとめ方のコツを徹底解説します。
中学生の自由研究|「簡単」の本当の意味とテーマ選びのコツ
中学生の自由研究で求められる「簡単」は、小学校低学年の「作業がすぐ終わる」とは意味が違います。
本当のポイントは、「考察がしやすい」こと、これに尽きます。
「1日で終わる」研究の落とし穴|作業と考察のバランス
多くの人が「1日で終わる」研究を探します。
しかし、作業があまりに単純すぎると、レポートに書くべき「結果」や「考察」が何も得られない事態になります。
中学生の研究では、ペットボトルで竜巻を作るような「現象の再現」だけでは評価されにくいです。
なぜそうなったのかを科学的に分析する「考察」こそが最も重要視されます。
おすすめテーマの選び方|「比較」できるものが最適
私がおすすめする「本当に簡単な」テーマとは、「作業は単純」でありながら「明確なデータが取れる」ものです。
具体的には、温度や濃度、材料の種類など、「条件を一つだけ変えて比較する」実験がベストです。
条件を変えて比較することで、結果の違いが明確になり、考察が非常に書きやすくなります。
「AとBを比べたら、Cという違いが出た。その理由はDだと考えられる」という論理的なレポートが書けます。
分野別おすすめテーマ一覧表
ここでは、作業が比較的簡単で、なおかつ「考察しやすい(=レポート推奨度が高い)」テーマを紹介します。
| テーマ | 理科分野 | 中核概念 | 推定時間 | レポート推奨度 |
| 10円玉をピカピカに | 化学 | 酸化還元 | 1時間 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 水に卵を浮かせる | 物理 | 密度、浮力 | 1時間 | 高 |
| ジュースからDNAを取り出す | 生物 | 遺伝子 | 1時間 | 高 |
| 唾液(消化酵素)の働き | 生物 | 酵素、消化 | 2時間 | 高 |
| スライム作り | 化学 | 高分子化学 | 1時間 | 中 |
| ペットボトルで夕焼け | 物理 | 光の散乱 | 30分 | 中 |
「低」評価のテーマは、現象は面白いものの、中学生が科学的に考察するのが難しく、「作ってみた」という感想文で終わりがちなものです。
【分野別】簡単なのに高評価!おすすめ実験テーマガイド
レポート推奨度が「高」だったテーマについて、具体的な実験の進め方と考察のヒントを解説します。
単なる「作業」を「研究」に格上げする視点が重要です。
化学編|10円玉ピカピカ実験(酸化還元)
10円玉のサビ(酸化銅)を落とす実験は、化学反応の速度を比較する優れた研究になります。
ただ「きれいにする」だけでは、5分で終わる作業です。
実験のポイント|酸と塩分で比較する
この実験の鍵は「比較」です。
(1) 酢、(2) レモン果汁、(3) 醤油、(4) ケチャップ、(5) ソース、(6) 水(比較対照)など、家庭にある液体を複数用意します。
「酸性度が強いほどきれいになる」という仮説を立てがちです。
しかし、実際には酸(酢)と食塩の両方を含むケチャップやソースが強力な効果を発揮します。
この「なぜ」を突き詰めるのが研究です。
考察のヒント
結果を「きれいになった順」でランキングにします。
「仮説では酸性の強さが重要だと考えたが、結果は違った。酢(酸のみ)より、酢と食塩を含むケチャップの方が圧倒的に速かった。このことから、10円玉のサビを落とす反応には、酸と塩分の両方が関わっていると考えられる」
このように、仮説と結果を比べて分析します。
化学編|スライムの性質研究(高分子化学)
スライム作りは「工作」で終わりやすいテーマの代表格です。
これを「科学」にするには、「物性」の変化を測定する必要があります。
実験のポイント|比率を変えて硬さを測定する
洗濯のり(PVA)とホウ砂の「比率」を変えて、5種類ほどのスライムを作ります。
「ホウ砂(架橋剤)の濃度が高いほど、スライムは硬くなる」という仮説を立てます。
その「硬さ」や「弾力」を数値化します。
例えば、「30cmの高さから落としたときの、跳ね返った高さ(cm)」や「1分間で垂れ下がった長さ(cm)」を測定します。
考察のヒント
ホウ砂濃度と「跳ね返った高さ」をグラフにします。
「ホウ砂濃度1%では跳ね返らなかったが、5%では10cm跳ね返った。この結果は仮説を支持している。ホウ砂がPVA分子の『橋渡し』の役割を果たし、その密度がスライムの弾力性を決めていることがわかった」
このように、データに基づいて結論を導きます。
物理編|卵を浮かせる実験(密度)
水に卵を浮かせる実験は、「密度」という目に見えない物理量を「数値化」する素晴らしい実験です。
ただ浮かせただけではデモンストレーションです。
実験のポイント|食塩の量で密度を「数値化」する
真水に沈む卵を用意します。
そこに食塩を10gずつ正確に計りながら溶かしていきます。
卵が水中に浮遊し始めた(または浮き上がった)瞬間の、「加えた食塩の総量」を記録します。
考察のヒント
結果から、その食塩水の「密度」を計算します。
例えば、水500ml(500g)に食塩60gで卵が浮いたとします。
密度 = 質量(500g + 60g) ÷ 体積(500ml) = $1.12 g/cm^3$
「卵が浮き始めたときの食塩水の密度は約 $1.12 g/cm^3$ であった。したがって、この卵の密度は $1.12 g/cm^3$ と推定できる」
これが「定量化」です。
生物編|DNA抽出実験
ブロッコリーやジュースからDNAを取り出す実験は、非常にインパクトがあり、レポートも書きやすいテーマです。
生命の設計図が目に見える瞬間に立ち会えます。
実験のポイント|身近な食材から取り出す
材料は、ブロッコリー、食器用洗剤、食塩、冷やしたエタノールです。
手順は「すり潰す」「混ぜる」「濾(こ)す」「静かに注ぐ」だけです。
水(濾液)とエタノールの境界面に、白い綿のようなDNAが浮かび上がってきます。
考察のヒント
「なぜ」その操作が必要だったかを一つずつ分析します。
「すり潰す」|細胞壁を壊すため。
「洗剤」|細胞膜(脂質)を溶かすため。
「食塩水」|DNAを溶かしやすく、安定させるため。
「エタノール」|DNAはエタノールに溶けない性質を利用し、目に見える形で取り出すため。
これらの役割を調べることで、細胞の構造とDNAの性質を深く理解できます。
実験キットを「研究」に格上げする賢い使い方
市販の実験キットは非常に便利です。
しかし、中学生が使う際には注意が必要です。
キットの「罠」に注意|説明書通りはNG
多くのキットは小学生向けに作られています。
説明書通りに「レモン電池を作ってLEDを光らせた」だけでは、「説明書を読んだ」だけであり「研究」とはみなされません。
私がいつも気をつけているのは、キットを「ツール(道具)」として使うことです。
キットを格上げする「比較」の視点
キットを使って「自分だけの仮説」を検証します。
例えば、レモン電池キットなら、
- 悪い例|「レモンでLEDが光った」
- 良い例|「仮説|果物の酸性度が強いほど高い電圧が出るはずだ」実験|キットの電圧計を使い、(1)レモン、(2)リンゴ、(3)ジャガイモ、(4)備長炭など、複数の材料の電圧を「測定・比較」する。
水のろ過キットなら、
- 悪い例|「汚い水がきれいになった」
- 良い例|「仮説|ろ過材の中で活性炭が最も濁りを取る効果が高いはずだ」実験|ろ過材を (1)砂利のみ、(2)砂のみ、(3)活性炭のみ、と条件を変えて、ろ過後の水の透明度を「比較・分析」する。
評価が上がる!自由研究レポート(まとめ)の書き方
どんなに素晴らしい実験をしても、レポートの構成が間違っていると評価はされません。
科学的な論文の「型」に沿って書くことが絶対条件です。
レポートの基本構成|8つの項目を押さえよう
自由研究のレポート(まとめ)は、以下の8つの項目で構成するのが標準です。
- テーマ名
- 動機と目的(なぜ、何を明らかにするか)
- 仮説(結果の予想)
- 準備したもの
- 研究の方法(手順)
- 実験結果(データ、表、グラフ)
- 考察(最も重要)
- 感想と今後の課題
差がつく「動機・仮説・考察」の書き方
評価者が最も重視するのが「動機」「仮説」「考察」の3点です。
これらは、一つの物語として連動している必要があります。
- 動機|「なぜ」その研究をしようと思ったか。(例|10円玉が汚れていた)
- 仮説|動機に基づき、自分なりの「予想」を立てる。(例|酸性の液体ならきれいになるはずだ)
- 考察|「結果」と「仮説」を比べる。(例|仮説は正しくなかった。酸性度よりも、酸と食塩の両方があることが重要だとわかった)
最も悪い考察は、結果をそのまま書くことです。
「ケチャップが一番きれいになった」これは「結果」です。
「なぜケチャップが一番だったのか、仮説と比べてどうだったか」を科学的に分析するのが「考察」です。
伝わるポスター(模造紙)作成のコツ
ポスター発表は「一目でわかる」ことが命です。
文章をダラダラ書かず、箇条書きやグラフ、写真を多用します。
レイアウトは「1. 目的」「2. 方法」「3. 結果」「4. 考察」のように番号を振り、読む順番を明確にします。
学術的なルールとして、
- 「表」のタイトルは、表の上
- 「図」や「写真」のタイトルは、図の下このルールを守るだけで、ポスターは格段に専門的に見えます。
まとめ|自由研究は「考察」がすべて
中学生の理科の自由研究を成功させる鍵は、テーマの珍しさではありません。
10円玉の実験や卵の実験のような「ありきたり」なテーマでも、「明確な仮説」を立て、「条件を変えて比較」し、「データに基づいて科学的に考察」する、という基本プロセスを忠実に実行することが、最も高く評価されます。
この記事を参考に、ぜひ「作業」を「研究」に格上げする、楽しい自由研究に挑戦してみてください。